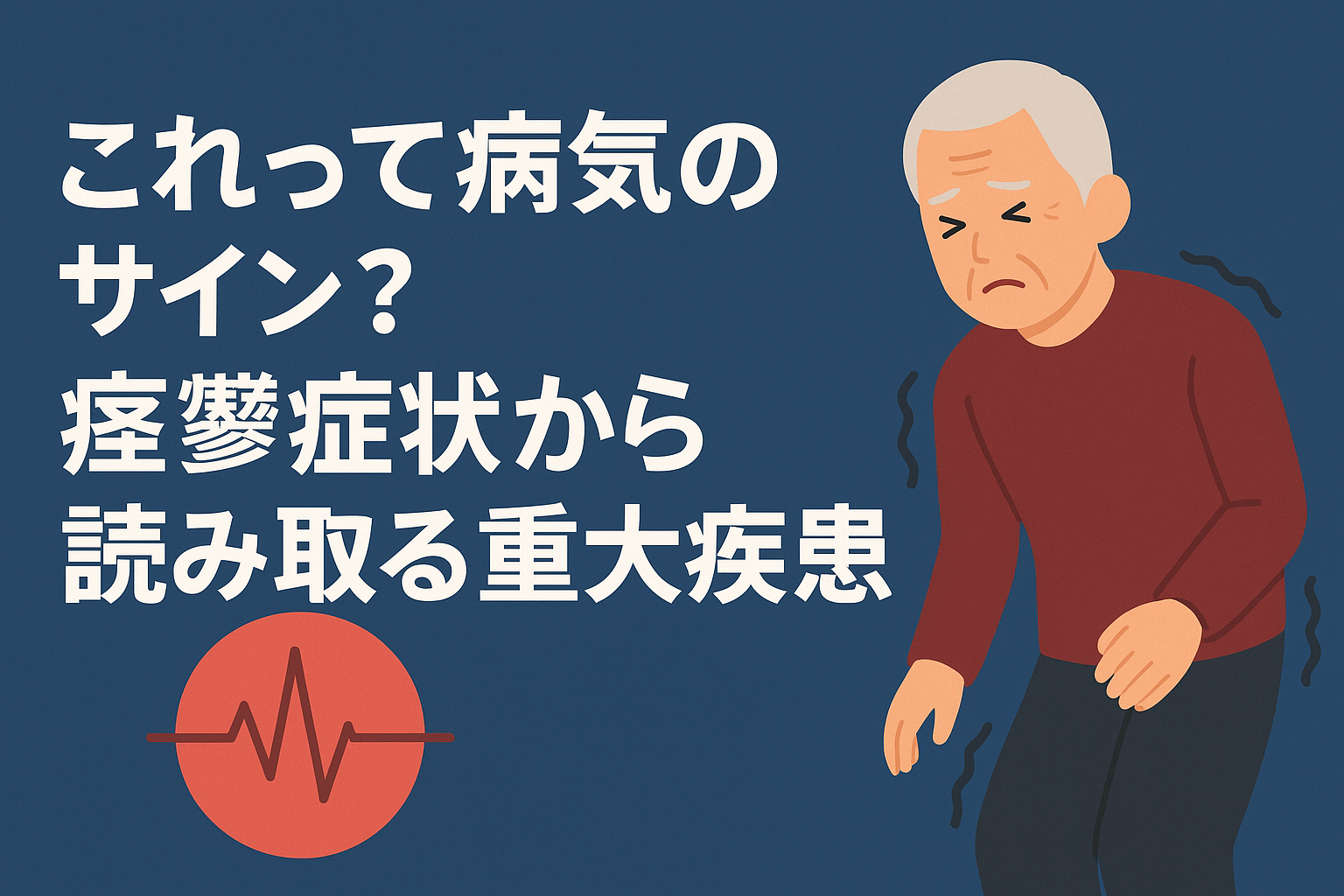今回は、徘徊の原因やリスク、家庭でできる予防策、徘徊発生時の対応方法、そして長期的な支援体制の整え方について解説します。
少しでも参考になれば幸いです。
徘徊のリスクとその背景を理解しよう
アルツハイマー型認知症と徘徊の関係
アルツハイマー型認知症の進行に伴い、徘徊行動は非常に起こりやすくなります。
認知機能が低下すると、場所や時間、人物の認識が曖昧になり、自宅にいても「帰宅しよう」と外出してしまうことがあるためです。
たとえば、自宅にいるにもかかわらず「家に帰らないと」と玄関から出ていくケースは典型的な例です。
また、買い物のために出たが、帰り道が分からなくなり、そのまま迷子になることもあります。
アルツハイマー型認知症において徘徊は非常に一般的な行動であり、事前の理解と対策が不可欠となるでしょう。
なぜ徘徊が起こるのか?主な原因とは
徘徊は主に不安や混乱、記憶障害が原因で引き起こされます。
認知症による短期記憶障害により、今自分がどこにいるのか、何をしているのかが分からなくなり、不安に駆られて歩き出してしまうのです。
「トイレに行こうと思っていたのに、目的を忘れてそのまま外に出てしまった」という行動は、原因が短期記憶障害にある一例です。
徘徊を防ぐためには、不安や混乱を和らげる環境づくりが重要であると考えられます。
徘徊による事故やトラブルのリスク
徘徊は事故や行方不明といった重大なリスクにつながる恐れがあります。
交通事故、転倒による骨折、寒さや暑さによる体調悪化など、徘徊には様々な危険が伴います。
実際に、冬場に外出した高齢者が低体温症で発見されるケースや、道路を無意識に歩いて事故に巻き込まれる事例も報告されています。
徘徊によるリスクを軽減するためには、早めの発見と対策が欠かせません。
徘徊を防ぐためにできる家庭内の工夫
玄関や窓への工夫と安全対策
玄関や窓には徘徊防止のための工夫を施すことが重要です。
簡単に外に出られないようにすることで、徘徊行動を未然に防ぐことができるためです。
チャイルドロックを取り付けたり、玄関にベルやアラームを設置して開閉時に音が鳴るようにすることで、家族がすぐに気付ける仕組みを作ることが効果的です。
ただし、出られないようにすることで、身体拘束とみなされることもあり、注意が必要です。
小さな工夫で徘徊リスクを大きく減らすことができると考えられます。
室内環境を整えて安心できる空間作り
本人が安心して過ごせる室内環境を作ることが徘徊予防に繋がります。
不安や混乱が少ない環境では、徘徊の動機となる焦燥感が抑えられるためです。
本人の好きな写真や馴染みの家具を配置し、環境を「自分の居場所」と認識しやすくする工夫が有効です。
室内環境の整備は、徘徊行動の頻度を減らす効果が期待できます。
GPS機器や見守りサービスの活用
万一徘徊が起こった場合に備え、GPS機器や見守りサービスを活用することが重要です。
早期に居場所を特定できれば、事故や迷子のリスクを最小限に抑えられるためです。
GPS付きの靴やタグ、スマートフォンアプリによる位置情報確認サービスがあり、徘徊が発生しても迅速に発見できる支援ツールとして広く活用されています。
最新技術を取り入れることで、家族の安心感も大きく向上すると考えられます。
広告
 | しにあどこ Airtag エアタグ 認知症 ご老人 徘徊 gps 首輪 GPS 充電不要で1年使える 老人 トラッカー ロケーター エアータグ 送料無料 価格:6979円~ |
徘徊が起きたときの対応方法
落ち着いて探すために必要な準備とは?
徘徊が起こった際には、慌てず冷静に行動するための事前準備が重要です。
事前に情報や手段を用意しておくことで、迅速かつ的確な対応が可能になるためです。
本人の写真を常に手元に用意しておく、よく行きそうな場所をリストアップしておく、周囲の人に顔を覚えてもらうなどの対策が有効です。
徘徊発生時に落ち着いて行動するためには、日頃からの準備が欠かせないと考えられます。
警察や地域への連絡方法
徘徊発生時には、速やかに警察や地域の支援機関に連絡することが大切です。
捜索範囲を広げ、発見の可能性を高めるためには専門機関の力を借りる必要があるからです。
警察へは「行方不明者届」を提出し、地域包括支援センターや民生委員にも協力を仰ぐことで、地域ぐるみの捜索が可能となります。
迅速な連絡と地域との連携が、徘徊による重大事故を防ぐ鍵となると考えられます。
発見後の対応と家族の心構え
発見後は本人を責めず、安心させる対応が最も重要です。
本人も混乱して不安な状態であるため、叱責はさらなる不安や徘徊の頻発につながる恐れがあるためです。
「心配したよ」「帰ってきてよかったね」と優しく声をかけ、安心感を与えることがポイントです。
発見後の対応は、今後の徘徊行動にも影響を与えるため、慎重に行うことが求められます。
長期的に考える徘徊対策とサポート体制の構築
地域包括支援センターとの連携方法
徘徊対策には、地域包括支援センターとの連携が非常に有効です。
地域包括支援センターは、徘徊高齢者に関する情報共有や支援体制の整備を行っているためです。
「高齢者あんしんセンター」などで、事前登録をしておくことで、万一の徘徊時にスムーズな対応が可能になります。
地域包括支援センターや民生委員、自治体、福祉事業所などと連携し、地域全体での捜索体制を整えることが、早期発見・保護につながります。
実際に、自治体による「見守りSOSネットワーク」や、地域包括支援センターを通じた情報共有・協力依頼が行われています。
地域資源を積極的に活用することで、徘徊リスクを大きく低減できると考えられます。
ケアマネジャーや介護サービスの活用法
ケアマネジャーや介護サービスを活用して、専門的なサポートを受けることが重要です。
専門家の視点から、本人に適した対策やサービスを提案してもらえるため、家庭内だけで抱え込む必要がなくなるためです。
デイサービスの利用で外出願望を満たしたり、訪問介護で家庭内の安心感を高めたりするなど、状況に応じた支援を受けることが可能です。
ケアマネジャーと連携し、適切な介護サービスを選択することが、徘徊リスクの軽減につながると考えられます。
家族自身の負担を減らすための支援制度
家族の負担を減らすためにも、支援制度を積極的に利用するべきです。
介護疲れが家族の健康を害し、結果的に本人にも悪影響を及ぼすリスクがあるためです。
介護休業制度や、短期入所(ショートステイ)の利用、認知症介護家族向けの相談窓口など、活用できる制度は多く存在します。
支援制度を賢く活用することで、家族も無理なく長期的に介護を続けることができると考えられます。
まとめ
アルツハイマー型認知症における徘徊行動は、進行とともに高まるリスクの一つです。
徘徊による事故や行方不明を防ぐためには、家庭内の環境整備、GPS機器などの活用、そして地域や専門機関との連携が重要となります。
さらに、徘徊が発生した際には、慌てず冷静に対応し、本人の安心感を第一に考えることが求められます。
家族だけで抱え込まず、地域支援や介護サービス、制度を積極的に利用することで、本人と家族双方にとって安心できる環境づくりが可能となるでしょう。
長期的な視点で支援体制を整え、穏やかな生活をサポートしていきましょう。
広告