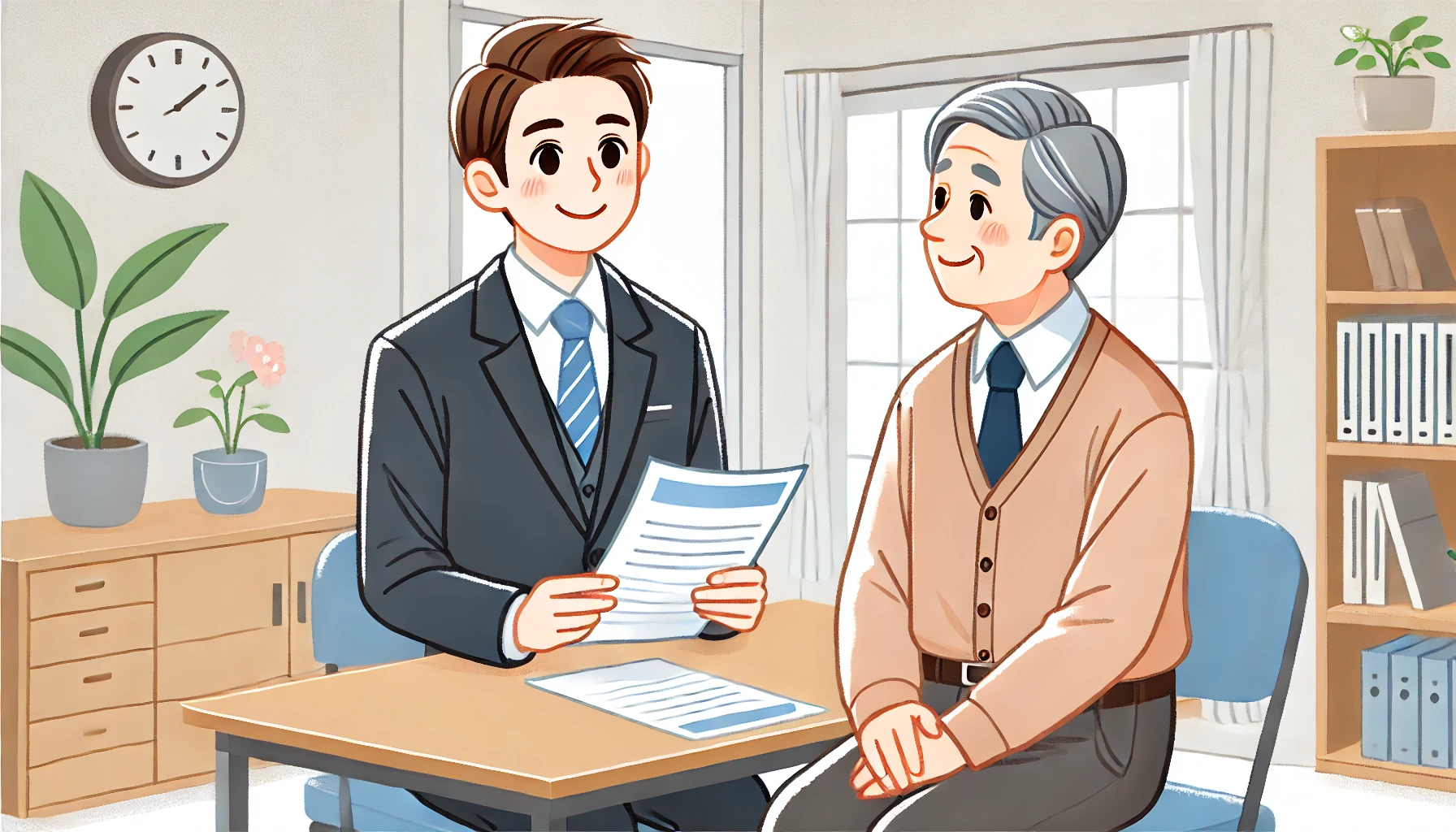認知症の進行や判断能力の低下に伴い、自身の財産や契約を管理することが難しい方が増えています。
ここでは、後見人制度の仕組みや、そのメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
後見人制度とは何か?
後見人制度の基本的な仕組み
後見人制度は、判断能力が低下した方の財産を守り、生活を支援する制度です。
制度には2種類あります
- 法定後見制度:家庭裁判所が後見人を選任します。
- 任意後見制度:本人が判断能力があるうちに、後見人を指定して契約を結ぶ制度です。
制度が必要となる背景
厚生労働省によると、2024年時点で認知症を有する高齢者の割合は全体の16%を超えています。
この状況により、詐欺被害や財産トラブルが深刻化しています。
後見人制度のメリット
財産と権利の保護
後見人制度を利用することで、詐欺や悪徳商法の被害を防ぎます。
また、後見人が適切な財産管理を行うため、不正利用のリスクも減少します。
介護・医療手続きの円滑化
介護施設への入所契約や医療サービス利用時の手続きを後見人が代行できます。
これにより、スムーズに必要な支援が受けられるようになります。
家族の安心感
後見人による公正なサポートは、家族の心理的な負担を軽減し、安心して日常生活を送るための土台となります。
後見人制度のデメリット
制度利用のコスト
後見人の報酬や手続き費用は、本人の財産から支払われます。
財産額によっては月額数万円が必要となる場合もあります。
手続きの複雑さ
後見人の選任には家庭裁判所への申立てが必要であり、診断書や専門家の助言が欠かせません。
これらの準備には時間と労力がかかります。
家族間トラブルの可能性
後見人の選任や財産管理を巡り、親族間で意見が対立することがあります。
これを防ぐためには、事前に家族で十分な話し合いを行うことが重要です。

後見人制度を最大限活用するために
適切な制度の選択
後見人制度を利用する際は、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
任意後見契約を結ぶ際には、公証役場での手続きが必要です。
家族間の合意形成
信頼できる後見人を選ぶためには、家族間での話し合いが重要です。
すべての関係者が納得する体制を整えましょう。
継続的なサポート体制の確立
後見人は家庭裁判所への定期報告が求められます。
透明性のある財産管理を維持するための仕組みづくりが必要です。
まとめ
後見人制度は、認知症や判断能力低下により困難を抱える方々の生活を守るための有力な制度です。
しかし、制度には利用コストや手続きの複雑さといった課題も伴います。
家族や専門家と相談しながら準備を進め、安心して制度を活用できるようにしましょう。
広告
 | 価格:7150円 |
 | 【POD】一から学ぶ成年後見制度 〜地方で働く司法書士が教えます〜(ブックトリップ) [ 俣野 裕哉 ] 価格:1342円 |