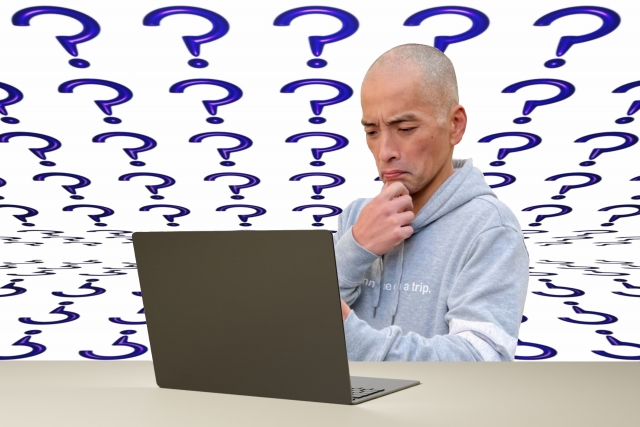今日銀行にお金を下ろしに行きました。
すると朝一にもかかわらず先客がいました。
その方が銀行から出たところで、自転車と衝突した音がしました。
見ると自転車に乗ったおばさんが、おじさんに謝っていました。
おじさんは大丈夫ですとすぐに立ち去りましたが、何かあれば大問題ですよね。
今回は、自転車事故について解説します。
歩道での事故が多発する理由
歩道は安全ではない?実は多い自転車との接触事故
歩道は一見安全に見えますが、実際には歩行者と自転車の接触事故が多発しています。
特に、店舗の出入口付近では注意が必要です。
歩道は本来、歩行者のための空間ですが、自転車の通行も認められている場所があります。
そのため、スピードを出した自転車と歩行者が衝突するケースが増えています。
自転車対歩行者事故における衝突地点別歩行中死者・重傷者数をみると、歩道での衝突が43%を占めています。
また、自転車側の法令違反では、前方不注意や安全不確認が多く見られます。
特に、銀行やコンビニなどの出入口では、歩行者が突然歩道に出ることが多く、自転車側も避けきれないことが原因となります。
令和2年の自転車対歩行者の交通事故件数は2,634件で、平成28年と比較して15.5%増加しています。
高齢者が銀行の自動ドアから出た瞬間に自転車とぶつかり、骨折する事故も発生しています。
歩道は安全とは限らず、特に銀行や店舗の出入口では、歩行者も周囲の状況をよく確認することが重要です。
なぜ事故が起こるのか?銀行や店舗の出入口が危険な理由
店舗などの出入口は、歩道上の事故が起こりやすいポイントです。
その理由を理解し、安全対策を講じることが大切です。
- 視界の悪さ:店舗などから出るときは、死角が多く見通しが悪いです。
- ドライバーの誤認識:車道から歩道がよく見えると思い込み、十分な確認をしないことがあります。
- 一時停止の不徹底:一時停止をしないドライバーが多いです
店舗などの出入口は視界が悪く、歩行者・自転車の双方が気をつけなければならないポイントです。
歩行者と自転車、どちらが気をつけるべき?
歩行者も自転車も、お互いに注意し合うことで事故を防げます。
一方だけが注意しても事故は防ぎきれません。
歩行者は急に飛び出さないようにし、自転車は歩道ではスピードを落とすことが必要です。
横断歩道のない交差点(その直近)での事故の場合、基本過失割合は歩行者15%、自転車85%となるようです。
歩道上での事故を防ぐためには、歩行者・自転車の両者が安全意識を持つことが重要です。
銀行や店舗から出るときに気をつけるべきポイント
ドアを開ける前に確認すべきこと
店舗などから出るときは、歩道を横断する前に一時停止し、歩行者の通行を妨げないよう注意する必要があります。
ドアを開ける前に周囲の状況を確認し、突然飛び出さないようにすることが大切です。
道路交通法では、やむを得ず歩道を横切る場合、直前で一時停止し、歩行者の邪魔をしてはいけないと定められているようです。
ドアを開ける前に一呼吸置いて確認するだけで、安全性が大幅に向上します。
歩道に出るときの「安全確認」のコツ
歩道に出る際は、車道に出るときと同じように安全確認をする習慣をつけましょう。
自転車が思わぬスピードで接近していることがあり、不注意でぶつかるケースが多いためです。
「歩道に出る前に3秒止まる」というルールを実践することも効果があります。
歩道も「安全確認が必要な場所」と認識することで、事故リスクを減らせます。
視覚的に危険を回避するためのポイント
自分の存在をアピールし、相手(自転車利用者)に気づかせる工夫が重要です。
目立たないと自転車側も気づかず、衝突してしまう可能性があるためです。
夜間は反射材を身につけたり、明るい服を着るなどの対策も有効です。
「自分が見えているから大丈夫」ではなく、「相手に気づかせる」意識を持ちましょう。
自転車側の対策も重要!お互いに安全な歩道を作るには?
自転車利用者が守るべきルールとは?
自転車利用者も、歩道を通行する際にはルールを守ることが大切です。
道路交通法では、自転車が歩道を走る場合「徐行」が義務付けられています。
また、歩道上では「車道寄り」を通るよう定められています。
歩道上での事故の多くは、自転車のスピード超過や歩行者の不意な動きが原因となっています。
ルールを守ることで、双方の安全を確保できます。
令和5年4月から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務が施行されました。
自転車利用者がルールを守ることで、歩行者との接触事故を減らすことができるでしょう。
歩行者と自転車が共存できる歩道の使い方
歩道は歩行者と自転車が共存する空間であり、譲り合いの意識が重要です。
自転車は基本的に車道を走るべきですが、歩道を通行せざるを得ない場合もあります。
そのため、お互いが注意しながら利用することが必要です。
自転車は原則として車道を通行しなければなりませんが、特定の条件下(13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体障害者、危険な状況など)では歩道を通行することができるようです。
歩行者が、歩道を歩く際、スマートフォンを見ながら歩いたり、自転車が歩行者の後ろでベルを乱用しないことや譲り合いの意識を持つことで、安全に通行できます。
自転車は歩道を通行する際、常に歩行者優先で、徐行しなければいけないことは知っておきましょう。
行政の取り組みと今後の改善
歩道での事故を減らすために、行政ができる対策も重要です。
歩道の安全性を高めるためには、インフラの整備や啓発活動が欠かせません。
- 自転車レーンの拡充
近年、各都市で車道に自転車専用レーンが増設されています。
これにより、自転車が歩道を走る機会が減り、事故リスクが低下します。 - 視認性の向上
銀行や店舗の出入口周辺にミラーを設置することで、歩行者と自転車がお互いの存在を確認しやすくなります。 - 啓発活動の強化
学校や地域での交通安全教育を充実させることで、子どもの頃から安全意識を高めることが可能です。 - 歩車共存道路の導入
欧州では環状道路や外周道路の整備に伴い、ゾーン対策が実施されています。
例えば、「ゾーン30」や「出会いゾーン」などの導入が進められています
行政が積極的に対策を講じることで、歩道上の事故は大幅に減少するでしょう。

もし歩道で事故に遭ったらどうする?
事故が起こった際の対応手順
万が一、歩道上で事故が発生した場合は、適切に対応することが重要です。
冷静に対処しないと、後でトラブルに発展する可能性があります。
事故が起こった場合の基本的な対応手順
- ケガの確認と安全確保
相手や自分がケガをしていないか確認する。
負傷者がいる場合、状況に応じて救急車を呼び、応急手当・救命措置を行います。 - 警察に連絡
小さな事故でも警察に届け出て、「交通事故証明書」を発行してもらうことが重要です。 - 相手の情報を確認
氏名、連絡先、自転車の場合は車体番号などを控える。 - 目撃者の確保
可能ならば第三者の証言を得ておく。 - 保険の確認
自転車側が自転車保険に加入しているかを確認。
事故に遭った際は、冷静に対処し、必要な情報を確実に記録しておくことが大切です。
過失割合はどうなる?知っておきたい法律知識
歩道上の事故でも、過失割合はケースによって異なります。
一般的に、歩行者と自転車では「自転車側により大きな責任がある」とされますが、状況次第で過失割合は変わります。
歩行者と自転車の事故
・歩道上や横断歩道上の事故:歩行者0%、自転車100%が基本。
・道路横断中の事故:歩行者20%、自転車80%が基本。
歩行者と自動車の事故(横断歩道)
| 信号機なし | 歩行者0%、自動車100% | |
| 信号機あり | 歩行者青信号 | 歩行者0%、自動車100% |
| 自動車赤信号 | 歩行者20%、自動車80% | |
| 自動車青信号 | 歩行者70%、自動車30% |
基本過失割合は以下の要素で修正されることがあります:
・夜間横断:歩行者の過失+5%
・幹線道路横断:歩行者の過失+5%
・住宅街・商店街:歩行者の過失-10%
・児童・高齢者:歩行者の過失-10%
・幼児・身体障害者:歩行者の過失-20%
※過失割合は複雑で、個々の状況によって変わりますので、正確な判断には弁護士への相談が推奨されます。
事故後に取るべき行動と示談のポイント
- 軽微な事故でも示談書を作成する
口約束だけでは、後から言い分が変わることがあります。 - 医師の診断を受ける
ケガがある場合は、必ず医師の診断を受け、診断書を取得する。 - 保険会社を通じて解決する
自転車保険や個人賠償責任保険を利用することで、スムーズに示談を進めることが可能。
見た目が軽傷であっても、必ず病院で診察を受けるようにしてください。
また、警察への連絡を怠ると、後日現れた身体の痛みに対する補償が受けられなくなるなどトラブルの原因になる可能性があります。
事故後の対応を慎重に行うことで、余計なトラブルを避けることができます。
まとめ
銀行や店舗の出入口は、歩道上の事故が起こりやすい場所です。
しかし、歩行者と自転車の双方が注意を払い、行政も適切な対策を行うことで、事故を減らすことが可能です。
万が一事故に遭った場合も、冷静に対応し、適切な手続きを踏むことが重要です。
広告