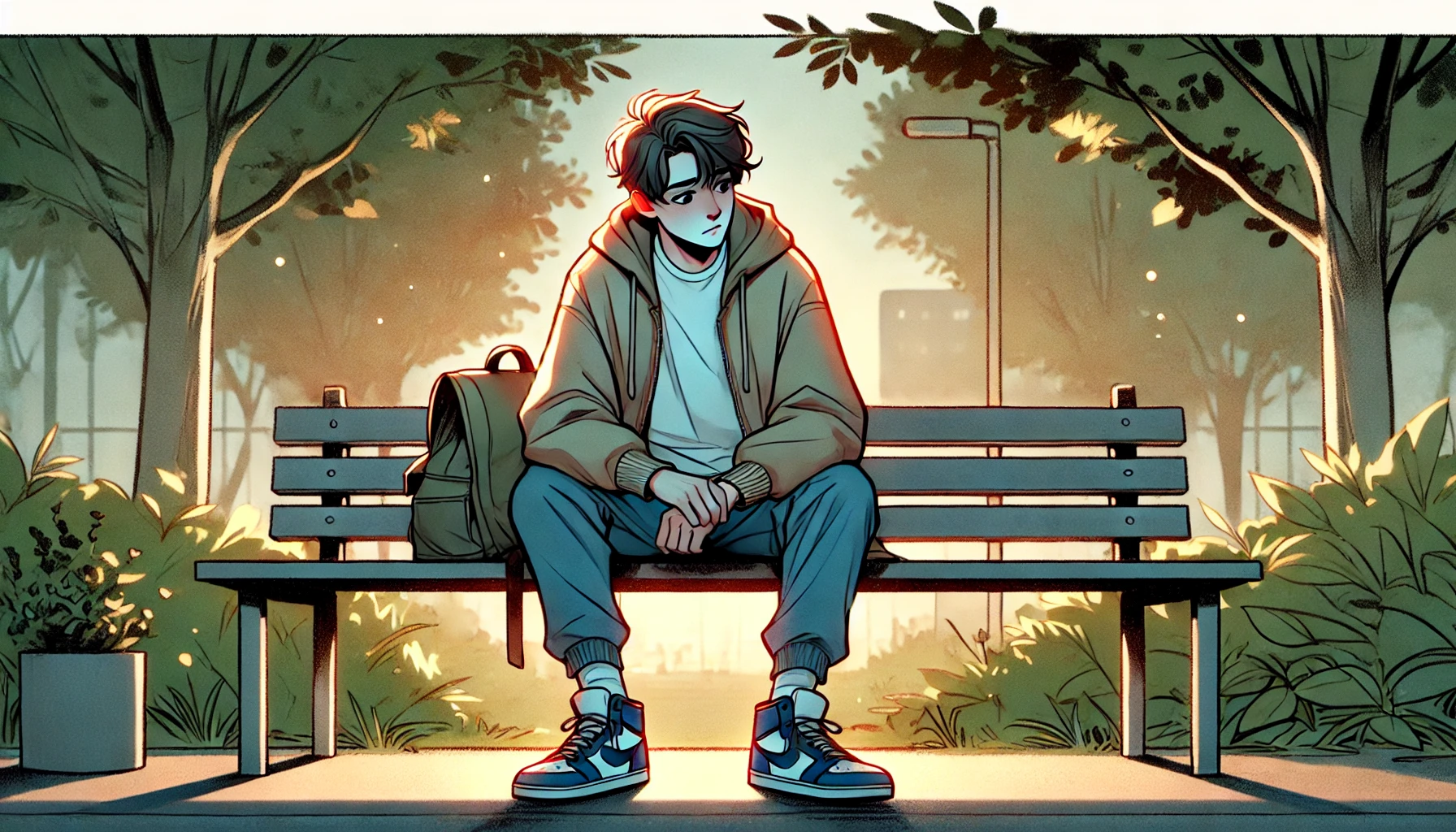日本は、他の国と比べても自殺者が多い国のひとつです。
長時間労働や経済的な不安、人間関係の悩みなど、さまざまな要因が重なり、多くの人が「生きることが辛い」と感じています。
特に、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え込んでしまうケースも少なくありません。
私自身、この現状を知るにつれて、「なぜこんなにも多くの人が自殺を選んでしまうのか?」という疑問を持ちました。
そして、少しでもその理由を知り、何かできることはないかと考え、この記事を書きました。
この記事では、「死にたい」と思う理由やその心理状態、そして周囲ができるサポートについて解説していきます。
大切な人が悩んでいるとき、またはあなた自身が辛いときに、少しでも役立つ情報になれば幸いです。
「死にたい」と感じる理由とは?
精神的なストレスが原因の場合
精神的なストレスが強くなると、「死にたい」と思うことがあります。
ただ「死にたい気持ち」を抱いている人の本音は、必ずしも死ぬことではなく、苦しい状況から逃れたいという願望であることが多いようです。
特に、長期間にわたるストレスは心の負担となり、逃げ場を失ったと感じやすくなります。
人間の脳は強いストレスを受けると、冷静な判断ができなくなります。
特に仕事や学校、人間関係の悩みが積み重なると、解決の糸口が見えず、極端な思考に陥ることがあります。
例えば、過労によって毎日長時間働いている人は、心身ともに疲弊し、「休みたい」という気持ちが「消えたい」という考えに変わることがあります。
また、いじめやパワハラを受けている場合、心の逃げ場がなくなり、生きることが苦しくなるケースもあります。
精神的なストレスが原因で「死にたい」と感じることは珍しくありません。
ストレスを軽減する方法を見つけることが重要です。
社会的な要因による影響
社会的な要因、例えば経済的な問題や孤独感が、「死にたい」という気持ちを引き起こすことがあります。
現代社会では、仕事や生活のプレッシャーが強く、人とのつながりが希薄になりがちです。
特に、経済的な困窮や家庭内の問題が重なると、希望を持ちにくくなります。
例えば、借金を抱えて返済の見通しが立たない人が、絶望感から自殺を考えることがあります。
また、高齢者の一人暮らしが増え、孤独を感じることで生きる意味を見失ってしまうケースもあります。
日本の若者の自殺の背景には、社会的孤立が大きな要因となっています。
またコロナ禍により、社会的孤立がより深刻化している可能性もあります。
周囲のサポートや公的な支援を活用することが大切です。
身体的な苦痛が引き起こす絶望感
慢性的な痛みや難病を抱えると、「生きることが辛い」と感じやすくなります。
身体の不調が続くと、生活の質が低下し、楽しみを見いだせなくなることがあります。
また、治療の負担や将来への不安も精神的な負担となります。
例えば、がんの末期患者が強い痛みに耐えながら生活していると、「この痛みから解放されたい」と考えることがあります。
また、障害を持つ人が社会的な偏見や不自由さに苦しむこともあります。
身体的な苦痛がある場合、適切な支援や治療を受けることが重要で、周囲のサポートや専門家の助言を求めることも推奨されています。
自殺を考えてしまう人の心理状態

希死念慮とは?自殺願望のサイン
「死にたい」と思う気持ちを「希死念慮」と言い、これが強くなると自殺のリスクが高まります。
希死念慮は一時的なものもあれば、慢性的に続くものもあります。
ただし、必ずしも自殺につながるわけではありません。
多くの人が人生のある時点で一時的に「死にたい」と感じることがあるとは思います。
特に、抑うつ状態にある人は、強い無力感や絶望感を抱きやすくなります。
例えば、「自分なんか生きていても意味がない」と口にする人は、心のSOSを発している可能性があります。
また、「消えたい」「誰にも迷惑をかけたくない」と言う場合も要注意です。
希死念慮がある人は、早めに誰かに相談することが大切です。
視野が狭くなってしまう心理的要因
自殺を考える人は、視野が狭くなり、他の選択肢が見えなくなることが多いです。
強いストレスや抑うつ状態になると、「もうこの状況を変える方法はない」と思い込んでしまいます。
本来なら助けを求めたり、状況を改善する方法を考えられるはずが、それができなくなります。
例えば、受験や仕事で失敗し、「人生終わった」と感じる人がいます。
しかし、時間が経てば違う道が開けることも多いです。
その瞬間の絶望感で未来を決めてしまうのは危険です。
2022年の調査では、18歳~29歳の若年層の約45%が「死にたい」と考えたことがあると回答しているようです。
これは、希死念慮が決して珍しいものではないことを示しています。
辛い時こそ、他の視点や可能性を探すことが大切です。
心のSOSを見逃さないために
自殺を考えている人の言動とは?
自殺を考えている人は、特定のサインを発していることが多いです。
「もうやっていけない」「もうどうでもいい」「すべてを終わりにしたい」などと言動や態度、外見行動に変化が表れることがあり、これを見逃さないことが大切です。
こうしたサインに気づいたら、早めに声をかけることが重要です。
「死にたい」と思ったときに試してほしいこと
感情を書き出して整理する
「死にたい」と思ったら、自分の気持ちを紙に書き出してみることが有効です。
考えが整理され、客観的に自分の状況を見つめ直すことができます。
- 「何が辛いのか?」をリスト化する
- 「本当に解決策はないのか?」を考えてみる
思考が整理されると、別の視点が見えてくることがあります。
専門家に相談する重要性
「死にたい」と感じるときは、専門家に相談することがとても大切です。
一人で抱え込まず、適切な支援を受けることで解決の糸口が見つかることがあります。
精神的に追い詰められていると、自分の状況を客観的に見ることが難しくなります。
しかし、専門家はそうした心理状態を理解し、適切なアドバイスや支援を提供してくれます。
医師やカウンセラーと話すことで、自分では気づかなかった解決策が見えてくることもあります。
例えば、うつ病の症状がある場合、精神科や心療内科の医師が適切な治療を行い、薬物療法やカウンセリングを受けることで気持ちが軽くなることがあります。
また、自治体やNPOが運営する相談窓口を利用すれば、無料でカウンセリングを受けられる場合もあります。
日本では、厚生労働省が「こころのオンライン避難所」を開設しており、自殺報道などに触れてつらい気持ちになった方のための情報を提供しています。
「死にたい」と思ったときに、専門家に相談するのは決して恥ずかしいことではありません。
むしろ、人生をより良い方向へ向かわせる大切な一歩となります。
自殺予防には「気づき、見守り、つなぐ」という3つの重要な要素があります。
周囲の人が変化に気づき、声をかけ、専門家につなぐことが大切となります。
生きることを諦めないでほしい
「死にたい」と思う気持ちは、決して珍しいことではありません。
誰しもが人生の中で、大きな苦しみや絶望を感じることがあります。
しかし、その気持ちが永遠に続くわけではなく、適切な支援を受けることで状況は変わる可能性があります。
あなたの存在は、必ず誰かにとって大切なものです。たとえ今はそう思えなくても、時間が経てば違う景色が見えてくることもあります。
どうか、一人で抱え込まずに、誰かに助けを求めてください。
広告